暇な時間があると、なんとなくスマホを触ってしまったり、
ダラダラと動画を見てしまったり…。

これまで、退屈に悩まされた方もいるのではないでしょうか?
「暇と退屈の倫理学」
こう言った退屈に耐えられないというのは、日常的なことで理解できますし、
そういう人が世の中の大多数だと思います。
暇な時間を何かでつぶしにいくということですね。
しかし、人によっては、スマホを観なくても時間をつぶすことができます。
このような差はどこから生まれてくるのでしょうか?
充実した日々を送りたいと思いつつも、
無為に過ごしてしまう自分に嫌気がさしてしまうこともあるかもしれません。

実は、この「退屈」という感情は、現代の消費社会において巧妙に利用されているのです。
そして、知らず知らずのうちに私たちを 貧しくしている側面があることをご存知でしょうか?
「退屈」については、國分巧一朗氏の「暇と退屈の倫理学」という本があります。

本書を踏まえつつ、我々を取り巻く消費社会の罠的な面からアプローチを行います。
今回は人間の2大不幸の一つである「退屈」を消費社会ではどのように利用されているのか、
それについてどう立ち向かっていくべきかについて考えてみたいと思います。
暇と退屈
まず、「暇」と「退屈」の言葉の定義です。
「暇」と「退屈」は異なる概念です。
・暇: 客観的な時間の空白。 スケジュールが何も入っていない状態。
・退屈: 主観的な気分。 何か物足りなさや刺激のなさを感じている状態。
「暇」と「退屈」は違うものですが、多くの人はこれを分けて使っていません。
「暇」、つまり客観的な時間的空白があった場合、
多くの人はその空白の時間を「なんだか退屈だな」と感じてしまうわけです。

これにより、多くの人にとっては「暇=退屈」となってしまいます。
一方で、「暇ではないが、退屈」というのも成り立ちます。
例えば、仕事をしていれば、その時間は埋まっていて、暇ではありません。
ところが、その仕事が単純作業になると退屈な気分になるでしょう。
つまり、「暇」ではない(=客観的な時間の空白はない)けど、「退屈」ということになります。
退屈の誕生と消費社会の罠
人類の歴史を振り返ると、定住生活を始める以前の人類は、
移動しながら狩猟採集をして暮らしていました。

生きるために常に頭を使い、新しい環境に適応していく必要があったため、
「暇」も「退屈」も存在しませんでした。
しかし、定住生活が始まると状況は一変します。
- 時間的な余裕、「暇」が生まれる
- 毎日の行動がルーティン化され、頭を使う量も減ることにより「退屈」になる
- 「暇で退屈」の形になる
ここで考えてほしいのが、人類の歴史です。
定住する前の移動生活(専門用語としては遊動生活といいますが)の時期は
400万年もあったのに対して、定住はたかだか1万年前からはじまったばかりです。
遊動生活をしている時期の方が圧倒的に長いわけです。
毎日毎日頭を働かせて生きていた刺激的な遊動生活の時代から、
定住へと生活スタイルを変更していくと、つねにフル回転していた頭脳からすると
物足りなくなってしまうわけです。
定住ですから景色も同じ、やることもだいたい同じ、
つまり刺激が少なくて退屈になるのですね。
そうなると人は刺激を求めていろいろなことをやりはじめます。
退屈をまぎらわせるために音楽やら踊りやら宗教やらと、
文化がどんどん開発されていきます。
そして、現代の消費社会では、企業はこの「退屈」を巧みに利用し、
私たちにお金を使わせる仕組みを作り上げています。
現代社会の「消費」
とくに現代では余暇が多くなっているので、レジャー産業が生まれてきます。
自分でどうやって暇をつぶすのかがわからない人たちは、
用意されたレジャーから選ぶという形になってきます。
自分のやりたいことがわかっていないので、
企業が用意した「なんか面白そう」なものにとびつき、お金を払います。
当然自分の本当にやりたいことではないので、満足度が低いわけです。
すると、「もっといいものはないか」と探し始め、どんどんレジャーの消費をおこないます。
しかしいくら消費しても、自分の本当にやりたいことではないので満足しません。
あくまで企業が用意したものなのですね。
こうやって消費はするけど、
いつまでたっても満足は得られないというのが消費社会の本質になります。
つまり消費社会ではユーザーが望むものを売っているわけではなくて、
企業が売りたいものを売っているだけなのですね。
ユーザーは用意されたものを買い続けているだけなので、
お金は払い続けるけどいつまでも満足が得られない、貧しい状態になります。

これはなぜかといえば、消費社会における企業は、記号や概念を売っており、
我々はそれを消費しているのです。
モノを使い倒したり、吸収して消費しているのではないのですね。
新製品やブランド品は、その記号や概念に価値を見出して購入することが多いですね。
例えば、スマートフォンの新モデルが発売されるたびに、多くの人々がそれを手に入れたいと思うのは、
新しさや先進性といった記号的な要素に魅力を感じているからでしょう。
一方で、本当に自分が求めているものや本当に満足できるものを見つけることは難しいことです。
退屈や空虚を感じる人々は、用意されたものに飛びついてしまうことがありますが、
その結果、満足感は得られず、さらなる消費が続くというジレンマが生まれています。

「新作」はいくらでも出せるので、きりがありません。
スマホゲームのガチャとかもこの原理を使っています。
記号や概念はいくら買っても満足しませんし、限度がないわけです。
企業側としては「満足しない」というのが重要なのですね。
こうやって消費社会では、暇のつぶし方のわからない「退屈」を感じる人たちに
記号や概念を売りつけます。
そしてそれらを買い続け、満足せずにひたすら貧しくなる人たちが量産されます。
いくら買っても心が満足しない、そんな状態になってしまう。
そして、企業は巧みなマーケティング戦略によって、
この「何かが足りない」という感情をさらに煽り、新たな消費を促すのです。
消費から「浪費」へ:真の豊かさとは
ここでこの「記号や概念」を買わされる我々は、企業にどうやって対抗するかについてですが、
『暇と退屈の倫理学』では「消費ではなく浪費をしろ」と述べています。
「贅沢」という言葉がありますが、これは「必要以上にモノを持つ」ということです。
必要最低限より多くのモノを持つことですね。
・浪費: 必要を超えてモノを受け取ること、吸収すること
例えば、
- 本を買ったら、内容を理解するまで繰り返し読む
- ゲームを買ったら、クリアするまで徹底的にやり込む
- 旅行に行ったら、その土地の文化や歴史を深く学ぶ
このように、モノや情報から最大限の価値を引き出すことで、
真の満足感を得ることができるのではないでしょうか?
消費社会の罠から抜け出すために
現代の消費社会は、私たちを「永遠に満たされない消費者」に仕立て上げようとしています。
しかし、私たちは「浪費する賢い消費者」になることができます。

そのためには、
1.「本当に必要なモノ」と「記号や概念に踊らされているだけのモノ」を見極める
2.モノや情報から最大限の価値を引き出すよう意識する
3.自分にとって本当に大切なことに時間とお金を使う
これらのことを心がけることで、消費社会の罠から抜け出し、
真の豊かさを手に入れることができるのではないでしょうか?
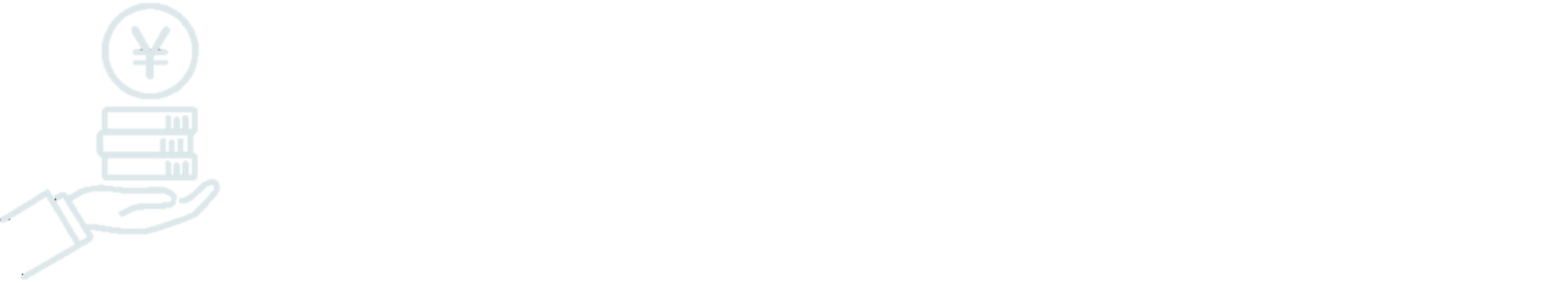
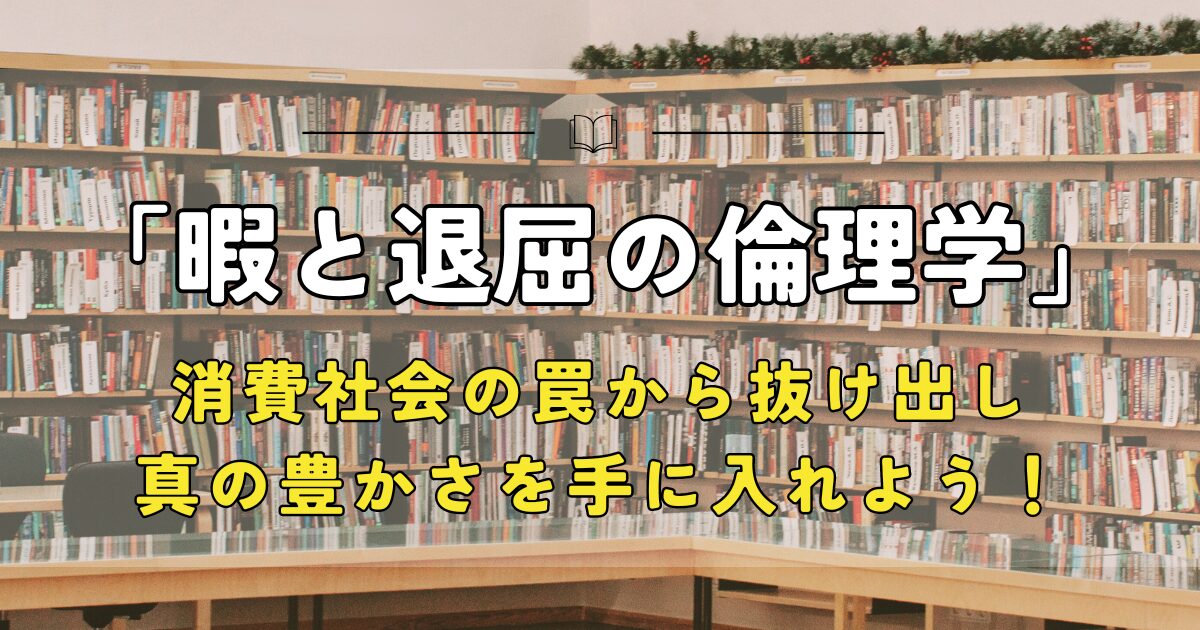


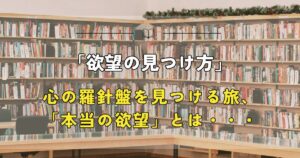
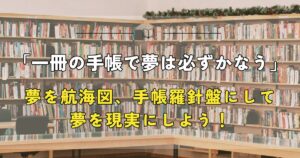
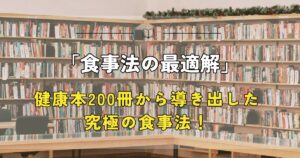
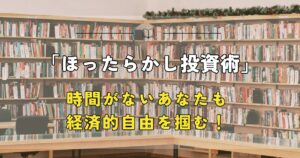
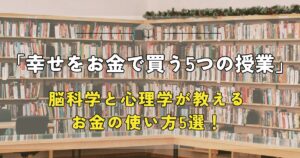
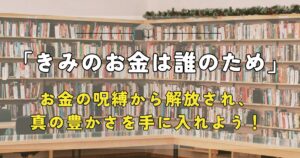
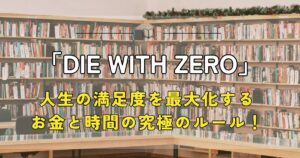
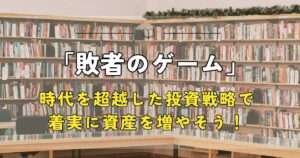
コメント